【曹洞宗】夫婦位牌の作り方・費用・納期まで詳しく解説
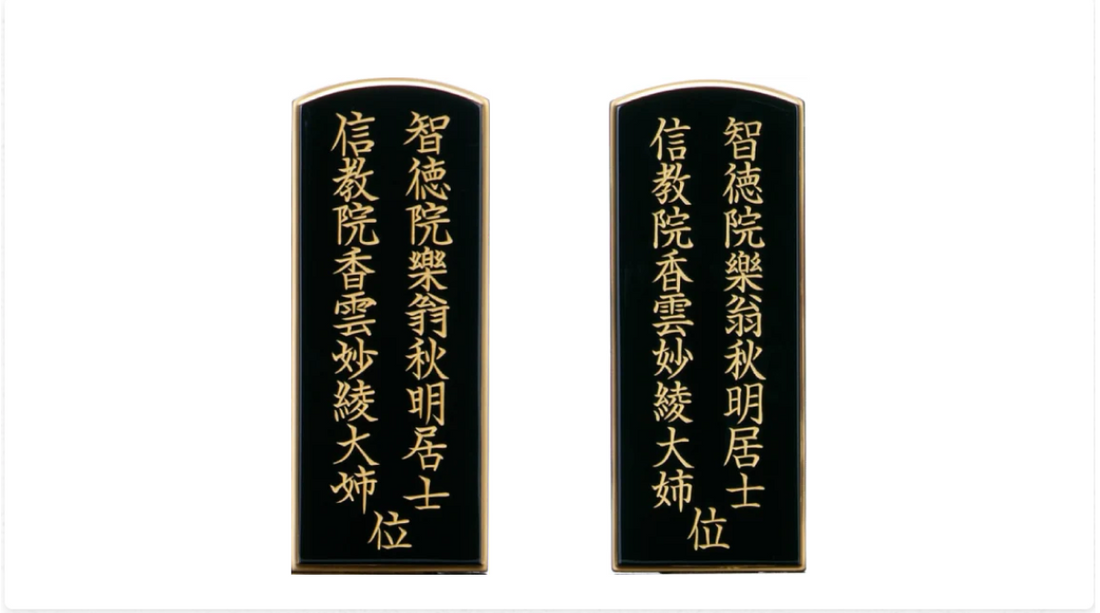
はじめに
夫婦でひとつの位牌を作ることはできるのか――。近年、夫婦で連名の位牌を用意したいと考える方も少なくありません。
この記事では、曹洞宗における夫婦位牌の基本から、作成の流れ、費用、納期、そして注意点までを徹底的に解説します。
1. 曹洞宗における夫婦位牌の考え方
曹洞宗は禅宗の一派で、只管打坐(しかんたざ)という座禅を重んじる宗派です。
曹洞宗における位牌は、亡くなった方の魂が宿るとされる大切な依代(よりしろ)であり、法要や日々の礼拝において中心となるものです。
本来、位牌は1名につき1つが基本とされますが、近年では夫婦の絆を重視し、1つの位牌に連名で刻む「夫婦連名位牌」を作る家庭も増えてきました。
2. 夫婦連名位牌の構成と表記例
位牌の構成は以下のように、片側に一人ずつ記す形式が一般的です。
【表面(表側)】
- 右側:先に亡くなられたご主人
- 例:○○院 △△ 顕道 居士
- 左側:のちに亡くなられた奥様
- 例:○○院 △△ 顕子 大姉
※生前にどちらも戒名を授かっている場合は、あらかじめ両方刻んでおくことも可能(逆修位牌)
【裏面】
- 俗名と享年(または行年)をそれぞれに記載。
- 例:
- 俗名 ○○ 太郎/享年八十五歳
- 俗名 ○○ 花子/享年八十二歳
※まだご存命の配偶者の欄は空白にしておくのが一般的です。
3. 夫婦位牌の作成タイミング
(1)一人目が亡くなられたとき
- 連名の位牌を作り、もう一人の欄は空白にしておく
(2)両方亡くなられたあと
- 既存の位牌を一対として残す方法:それぞれ個別に作成した位牌を並べて祀る
- または新しく連名位牌を作ってまとめ直す方法もあります
(3)33回忌や50回忌を機に
- 先祖代々位牌にまとめる家庭もあります
4. 曹洞宗のルールと注意点
曹洞宗では、戒名・没年月日・俗名・年齢などの書き方に形式があります。
● 代表的な注意点
- 「之霊位」「新帰元」は白木位牌のみ、本位牌では入れない
- 文字色(金文字・朱文字)は用途によって選ぶ
- 金文字は一般的に使用される標準的な文字色。
- 朱文字は生前に戒名を授かった場合(逆修)に使用され、生前戒名や俗名の部分のみを赤く記すことが多いです。
- 「享年(数え年)」か「行年(満年齢)」かの選択
- 享年は数え年(生まれた年を1歳とし、以後元日に1歳加える)で記載する方法です。
- 行年は満年齢(誕生日を基準に数える)です。
- 地域やご家庭の方針により使い分けられますが、既存の位牌に合わせると自然です。
- 曹洞宗では戒名を授かるのが一般的
5. 費用の目安と選び方
● 価格帯の目安(夫婦位牌・本位牌)
- 塗位牌:2万円~10万円程度
- 唐木位牌:3万円~10万円程度
- モダン位牌:2万円~8万円程度
● 位牌の種類(素材・仕上げ)
- 塗位牌:漆を使用。重厚で格式高い。
- 唐木位牌:紫檀や黒檀など天然木を使用。高級感あり。
- モダン位牌:家具調仏壇に馴染むシンプルなデザイン。
仏壇との調和や既存の位牌と合わせて選ぶのがおすすめです。
6. 納期と注文の流れ
● 通常納期
- 約10~14営業日
- 特注や彫刻加工によっては2~3週間かかる場合も
● 注文の流れ(例)
- 白木位牌などを参考に戒名・俗名・命日を確認
- 位牌の種類・サイズを決定
- 彫刻内容を注文時に記入
- 仕上がり確認・納品
白木位牌に記された情報を元に、誤記を防ぐことができます。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 戒名がまだないのですが、夫婦位牌は作れますか?
→ 片側のみ戒名を刻み、もう一方は空欄で作成可能です。生前戒名(逆修)を授けられた場合は、朱文字で記載されることがあります。
Q2. 宗派が異なる夫婦の場合は?
→ 合同位牌も可能ですが、宗派による戒名・作法の違いを尊重する必要があるため、まずはお手次のお寺にご相談ください。
Q3. 後から片方を追加刻印できますか?
→ 基本的には可能です。ただし、素材や加工方法によっては困難な場合もあるため、注文時にあらかじめ確認しましょう。
まとめ
- 曹洞宗では、夫婦位牌を作る家庭も増えてきた
- 書き方・構成にルールがあるので注意
- 費用は2~10万円程度、納期は2週間前後
- 白木位牌を元に内容確認しながら丁寧に作成
夫婦の絆を形にする位牌は、故人を偲び、家族の心をつなぐ大切なものです。正しい知識をもって準備することで、安心して供養を行うことができるでしょう。